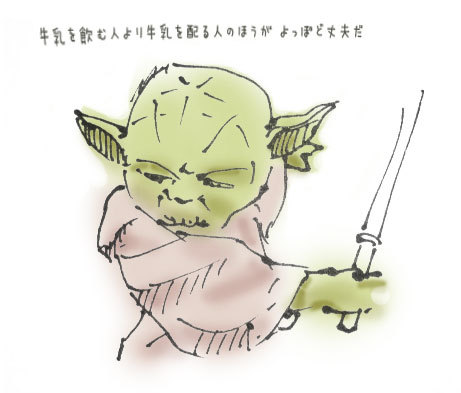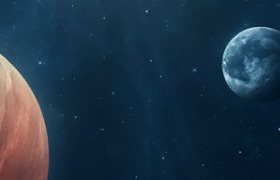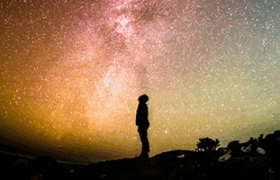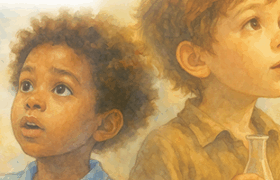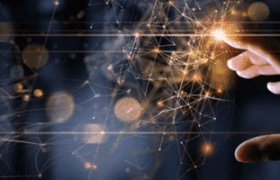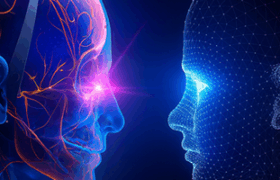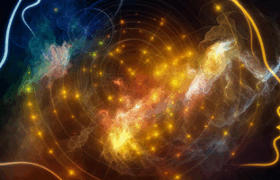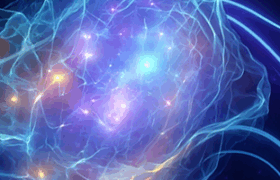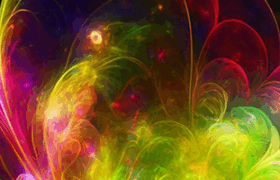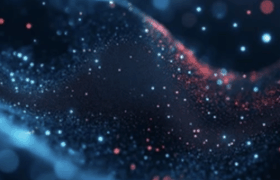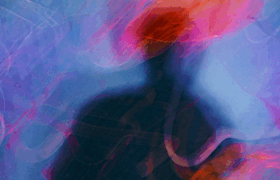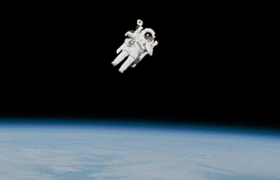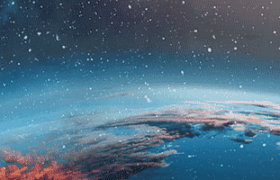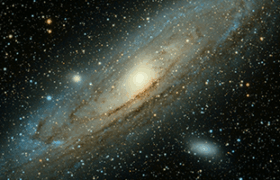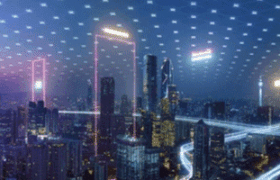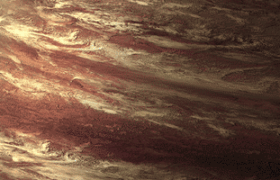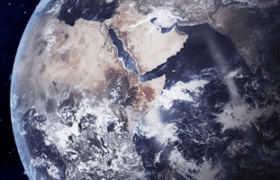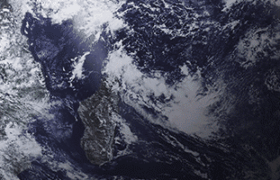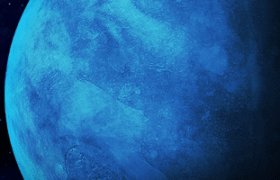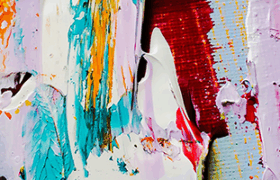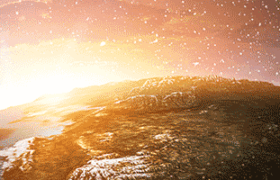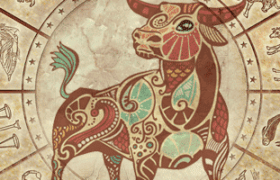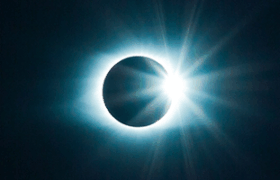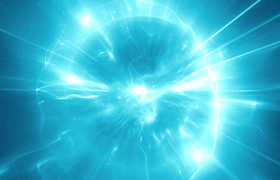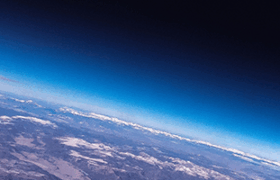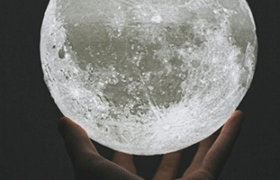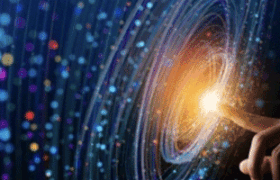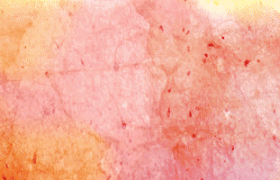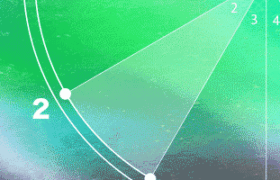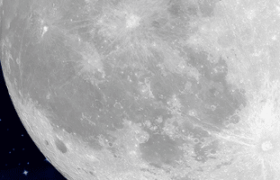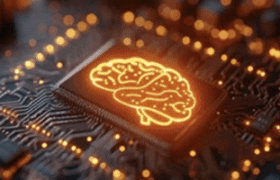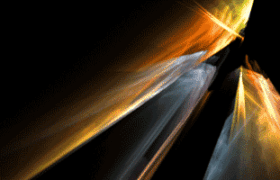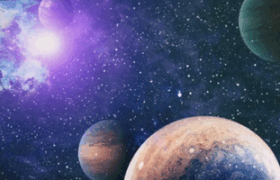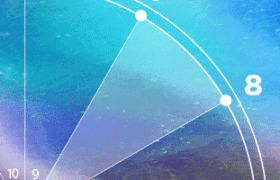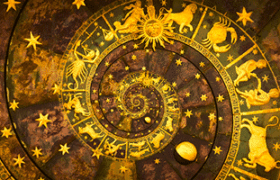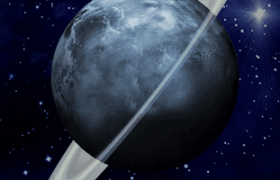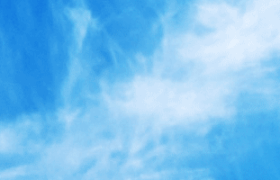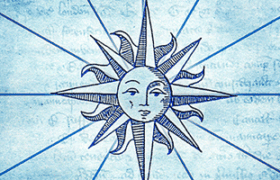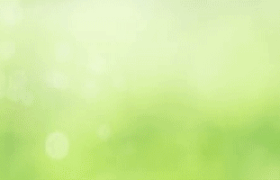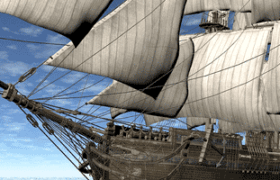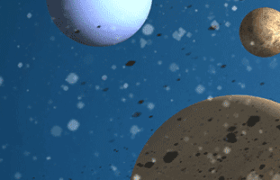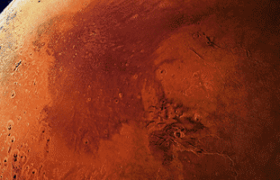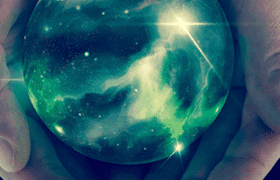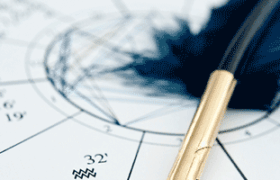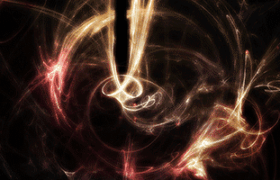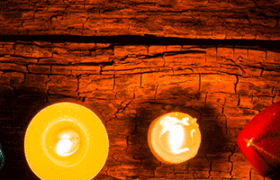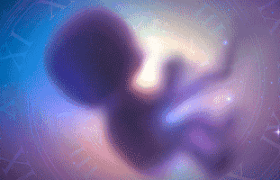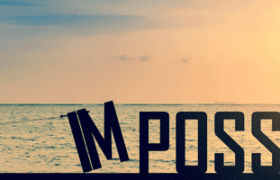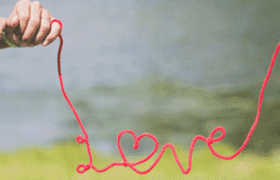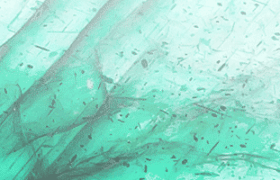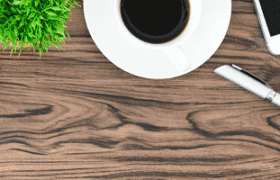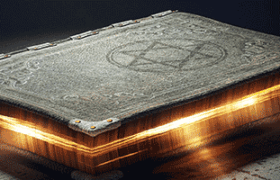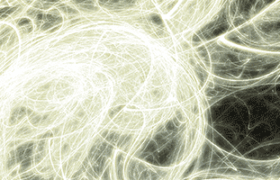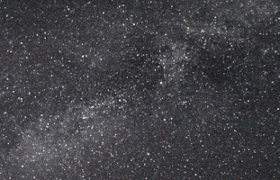シュタイナーはなんで12感覚を提唱した? 熱感覚って触覚じゃないの?

目次
シュタイナーはなぜ12感覚論を提唱したのか?

クォッカちゃん
ルドルフ・シュタイナーというのは、「12感覚論」を提唱した人だったね

占星術師Yoda
そう。彼は、私たちの感覚世界を独自の視点から捉え直そうとしたんだ。
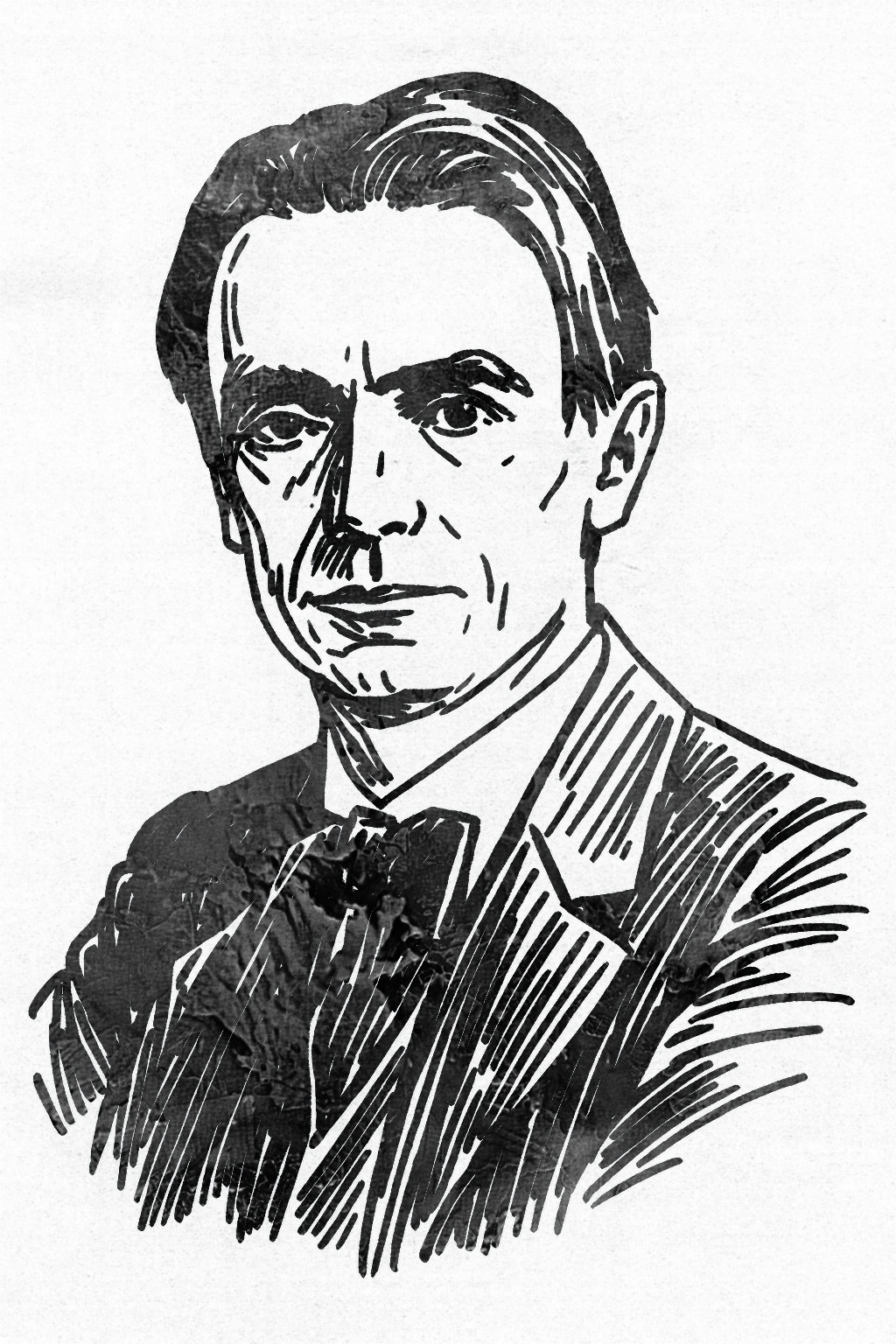 ルドルフ・シュタイナーの似顔絵
ルドルフ・シュタイナーの似顔絵シュタイナーの12感覚というのは、五感(味覚、視覚、嗅覚、聴覚、触覚)に加えて、運動感覚、平衡感覚、熱感覚、思考感覚、生命感覚、自我感覚、言語感覚の7つを加えたものです。
・・この分類をみると、
「熱感覚って触覚じゃないの?」とか思いますが、
じつは彼のいう"熱感覚"というのは、他者との共感とかも意味するんです。
(例えば、誰かといて「ぬくもりを感じる」「冷たい人だと感じる」=単なる物理的な熱ではないですよね?)
🔹 シュタイナーはこう考えた
シュタイナーは、人間存在というものを肉体・魂・霊の三層構造でとらえ、感覚はこれらの相互作用の橋渡しとして働くと考えていました。
現代的な「五感」や「生理学的感覚」とは異なり、シュタイナーの感覚論では、感覚は意識の表現であり、魂と身体をつなぐ霊的な器官のようなものと捉えたのです。
特に重要なのは、彼が以下の3つの層に分類したことです:
- 身体感覚(自己に関する)
- 外界感覚(外部世界を認識する)
- 社会的・霊的感覚(他者や霊的実在に向かう)
今回のコラムでは、
12感覚それぞれについてのシュタイナーの意図や背景に注目しつつ、詳しくみていきますね
1〜4:身体に関する感覚(内的な自己認識)
1. 触覚
「自分の限界」を知る感覚。物質的な境界に触れることで、「私がここまでだ」と認識する。
これは単なる皮膚刺激ではなく、自我が「ここから先は他者」と境界づける認識機能。
シュタイナーは、触覚を「物質的な自己感覚のはじまり」と捉えていました。
つまり、自分という存在が、この世界の中で"ここにいる"という実感。
触覚によって、わたしたちは「物質的な現実」に最初の一歩を踏み出すのです。
2. 生命感覚
身体全体の調和や不調を感じたり、「健康・不快・倦怠・活力」などを感じ取る感覚。
病気でなくても、「なんとなく疲れた」などもこの感覚です。
生命感覚は、「自分というひとつの生命体が、いまどんな調子か?」という全体的な内的気づきです。
それは、言葉になる前の「魂のざわめき」に近いかもしれません。
3. 運動感覚
自分の動き、筋肉の状態を意識せずとも感じられる感覚。
歩いたり、物を持ち上げるときの「重さの感知」などにも関係しています。
これは単なる運動神経ではなく、「意志」が身体を通して世界に働きかけるときの感覚です。
わたしたちは、「動こう」と思った瞬間に、自我を動きとして表現しているのです。
4. 平衡感覚
空間における自分の位置を知覚し、安定性を保つ感覚。
「転びそう」「揺れている」と感じるのは霊的に自我が安定を探る働きもあり。
シュタイナーにとって平衡感覚は、「わたしがこの地球上にまっすぐ立つ」ことを意識する、霊的な調整力でした。
重力と共に、世界と調和する力とも言えます。
5〜8:外界に向かう感覚(自然界との出会い)
5. 嗅覚
物質の「本質」や「腐敗・鮮度」といった、目に見えない変化を直感的に捉える感覚。
シュタイナーは、嗅覚を「見えないものを察知する最初の入り口」として重視しました。
たとえば、空気の中にあるごくわずかな違和感から、食べものの鮮度や場所の雰囲気、人の状態までも察知できたりしますよね。
この感覚は、物の“生命力”や“霊的な気配”にも通じていて、いわば「魂の鼻」のような働きをしているのです。
6. 味覚
物質の「内面」に直接触れる感覚。
飲み込む前に「これは体に取り入れていいか?」と、魂が判断するチェック機能のような役割もあります。
味覚は、シュタイナーにとって、外界と自分との最も直接的な境界面。
口に入れるという行為は、世界を自分の中に取り込む儀式でもあります。
「これは甘い」「これは苦い」──その背後には、「これは安心して受け入れられるかどうか」という魂の判断があるのです。
7. 視覚
物質の形態(かたち)や色、遠近感などを把握する感覚。
ただし、シュタイナーにとって視覚とは単に「目で見る」ことではありません。
そこには「距離を保って世界を見る」という魂の成熟」が関係しているのです。
わたしたちは、視覚を通じて「対象」と「自分」を分けて観察します。
このとき、自我は主観にのまれずに、客観的に世界を理解しようとする意志を働かせています。
8. 熱感覚
温度という物理的な要素を超えて、「その場のあたたかさ・冷たさ」を感じる感覚。
たとえば、人といて「なんだかあたたかい気持ちになる」とか、逆に「この人、冷たい感じがする」と思うこと、ありますよね。
それは魂の熱感覚がはたらいているのです。
シュタイナーにとって、熱感覚は「わたし」と「他者」の間の共感温度のようなもの。
ここには、物理的な温度だけでなく、こころのあたたかさや、関係性の熱量も含まれてきます。
9〜12:精神世界に向かう高次感覚
9. 聴覚
「音」を通して、目に見えない“こころの響き”や“意味”を受け取る感覚。
シュタイナーにとって、音はただの空気の振動ではなく、
魂と魂が共鳴し合う“霊的な現象”でした。
たとえば、音楽に感動して涙が出たり、声のトーンだけで相手の気持ちが伝わったり──。
音は、物質を超えて、わたしたちの魂に直接はたらきかける力を持っているのです。
10. 言語感覚
これは、音そのものではなく、「ことばのうしろにある意図や意味」を感じとる感覚です。
「何を言ったか」だけではなく、「どういう思いで語ったのか」「どんな感情がこもっていたのか」──それを“魂で聴く”力です。
シュタイナーは言語感覚を、「人と人とをつなぐ霊的な橋」と捉えていました。
言葉は、ただの情報ではなく、命が宿ったエネルギーなんですね。
11. 思考感覚
「相手がどう考えているか?」
「この人はどんな世界観でものを見ているか?」──
その思考のあり方そのものを“味わう”ように感じる感覚です。
これは、単なる理解や知識の共有ではありません。
他者の思考そのものに魂が触れ、その中で生きるような感覚なのです。
シュタイナーはこれを、「魂が他者の“概念の世界”に入っていく力」と見ました。
つまり、思考の奥にある霊的な構造を知覚する感覚です。
12. 自我感覚
これは最も高次で霊的な感覚。
相手の「本質」──つまりその人の魂・霊的個性そのものを、直接的に感じ取る感覚です。
たとえば、相手が何も語らなくても、ふと「この人は深く優しい人だな」と感じるようなこと。
それは、相手の“自我そのもの”に触れている瞬間かもしれません。
シュタイナーは、自我感覚こそが、真の人間同士の出会いを可能にする霊的な共鳴領域だと語っています。
この感覚は、愛・尊敬・あたたかなまなざしの中で育まれます。
シュタイナーの12感覚と12星座は対応する?
占星術師の松村潔さんは、このシュタイナーの12感覚と、12星座を独自に対応させています。
(シュタイナー自身は、12感覚と12星座の対応はしていない)
(※ 松村先生の12星座x12感覚の対応表はこちらのコラムで解説しております)
これは面白い試みだと思います。
ただ、やってみるとわかるけど、キッチリ対応はしません。
松村潔先生は、なぜ臭覚をみずがめ座と対応させたのだろう? などと考えると楽しいし、星座の理解が深まったりもします。
彼の著書には、けっこう頻繁に「やぎ座は平衡感覚に関係しています」といった記述がでてきます。
松村さんの本で占星術を学ぶときに、知っておくと便利なので、今回あらためてシュタイナーの12感覚をまとめました。
参考になれば嬉しいです^^
参考記事: